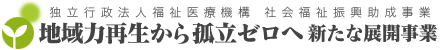1.事業の目的
高齢者が加齢や疾病による身体的機能の衰えとともに、一方的に支えられる側となることで、自信や自立心が失われ、日々の活動量が低下していくと、家に閉じこもりがちな生活となり、社会とのつながりが少なくなっていく。当然、心身状態の悪化もおこりうる。
本事業は、そんな社会的孤立状態にならない、させないことを目指して、「自ら能動的に支え手としてもいきいき活躍できる場」を創っていく支援事業である。
高齢者やその家族自身が担い手になって、生きがいづくり等の「場」を主体的に創造するための支援活動を、地域の多世代や既存団体等が連携して行う事で、衰退しつつある地域力再生の一助ともなり、自立支援、介護予防のみならず、互いに支え合うネットワークの構築にも寄与できるものと考える。
2.事業の背景
(1)事業実施地域の特性
当事業を展開した山梨県甲斐市は、周囲を山で囲まれた甲府盆地の中西部に位置し、都市化の進む平地地域と、移動手段に乏しい山間地域からなり、県内市町村では甲府市に次いで、2番目に人口が多い地域である。
中心部の平地地域は地縁、地域力の低下が進み、周辺山間部では、加齢に伴う歩行力低下による外出困難者が増加し、あちこちで孤立が進んでいる。
(2)利用したい介護予防や生きがい活動の支援サービスがない
高齢者ニーズ調査によると、力を入れてほしい高齢者施策として「介護予防・認知症予防の充実」を望む声が多く、介護予防の啓発や介護予防教室などの実施が求められている。一方で取り組むきっかけがないことや、具体的な取り組み方法がわからないことを理由に、介護予防に全く取り組んでいない方が調査対象者全体の半数を占め、「利用したい介護予防や生きがい活動の支援サービスがない」との回答者は3割にもなっている。(甲斐市第6次高齢者保健福祉計画第5期介護保険事業計画(平成24~26 年度)より)
すなわち居住立地環境から通えない、支援サービス内容からニーズに合わないなどの理由で、対象者が介護予防事業や生きがい活動に積極的に参加しづらい状況にあると考えられた。又参加してもその場限りの活動となってしまい、継続性につながらなかったりして、量的質的に不十分といわざるをえない状況である。しかし、こうした状況は一部地域に限ったことではなく、全国どこの市区町村においても、さまざまな努力はしているものの、なかなか解決できないジレンマとなっており、多様な環境や価値観等により複雑化するニーズに、どのように対応していくかは今後の重要な課題となっている。
(3)高齢者自身が主体的に関わる新しい取り組みの必要性
今後、さらに高齢者の増加、孤立が一層進むと予想されることから、ますます健康づくりや介護予防が欠かせないが、従来のようなお仕着せのやり方(行政や事業者から一方的に提供される画一的な内容や選択するメニューが少ないなど)のままでは、高齢者はいつまでも受動的で、積極的な健康づくりや介護予防に結び付きにくい。やはり高齢者自身が、自発的、かつ継続的に行うことができるための新しい取り組みと、支援体制づくりが必要と考えられ、今回の事業を展開することにした。
そこで、私たちが考える新しい取り組みと支援体制づくりを以下に示す。
3.私たちが考える新たな取り組み
1) 高齢者等の地域コミュニティへの参加促進による効果的な介護予防・自立支援策の創出
ⅰ)高齢者やその家族自身が支えられるだけでなく、支え手・担い手としていきいきと活躍できる「場」の創造
ⅱ)上記「場」づくりを実施しやすいように、きっかけ、具現化、立ち上げ、運営、維持、継続などのための支援体制の構築
2)地域で互いに支え合う信頼関係の構築による高齢者等の社会的孤立防止
ⅰ)地域との接点が少ない閉じこもりがちな高齢者や特定高齢者になりつつある方々等を早期に発見し、つながること
ⅱ)大規模災害時でも機能するような互いに支え合うネットワークの構築
(多世代や顔の見える交流機会の創出)
3)高齢者等が自発的に健康で豊かな人生の創造に取り組む意識の醸成
ⅰ)高齢者自身が健康づくりを自発的かつ継続的に行う取り組みの開発と支援体制の確立
ⅱ)生きがいや仲間づくり等精神的支えにつながる活動の推進
ⅲ)加齢や身体機能と関わりなく、自分の特技や能力をできる範囲で提供して人の役に立つ喜びを知る機会の創出
ⅳ)行政や事業者が主体となって事業者スタッフが高齢者に提供して参加してもらう従来の受動的スタイルから、事業者スタッフ等は支援者にまわり、地域の高齢者やその家族自身が主体者となる積極的・能動的スタイルへの転換