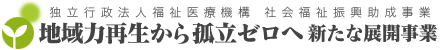高齢者やその家族が一方的に支えられる立場にいるだけでなく、「支え手」あるいは「担い手」となり、誰かを支えたり、役割や役目を担ったりして、社会の一員として活躍の場を持つことが生きる活力につながっていくことを本事業の実施により改めて認識することができた。
前述の実績などから本事業を通じて、以下の5点について成果・効果が得られたと考えられた。
1)高齢者が主体者となる「場」づくり
2)「場」を通じた社会的孤立防止
3)「場」づくり支援者・団体等との継続的な連携体制づくり
4)地域力の育成
5)「場」を通じた、介護予防、自立支援、認知症予防等高齢者の抱える課題解決
(1)意欲の高まり
加齢や持病などによる心身機能の衰えから、徐々に活動量や意欲が低下していくと、閉じこもりがちな日常生活に陥りやすく、その結果、さらに心身機能の衰えが進むという悪循環を招くことになりうる。
そうした負のサイクルに陥らないために、心身機能の衰え自体をなんとかしようとすると、①若い頃から、加齢に負けない身体づくりや、生活習慣病を始めとする病気の予防、早期発見など、健康に留意した日常生活を送ること、②現状以上心身機能を衰えさせないよう、維持を目的とした運動や、機能訓練を定期的に生活に取り入れることなど、できるだけ衰えるスピードを遅らせたり、衰えないよう鍛えたりするような直接アプローチとなる。このことは、必要不可欠な取り組みであり、意識して継続的に行っていくべきことであるが、前述の調査結果等を見ても、現実的にはなかなか容易なことではないようである。
そこで、楽しみや生きがいなど、進んで行いたくなるような仕掛けを施して、自然に活動量や意欲を向上させることにより、心身機能の衰えを防ぎ(間接アプローチ)、できるだけ、健康で活力ある豊かな生活を送れるよう、支援することが、本事業のねらいでもあった。では、閉じこもりがちな高齢者がどのようなことに興味を持ち、どのようなことであれば、主体者として関わりたくなるのか、「場」の開催時など機会ある毎に、ヒヤリングや反応を調査したところ、以下のように考えられた。
①社会性のある活動(使命、メッセージ、人の役に立つこと)
②自分らしく自分の存在が発揮できる活動(居場所の発見、生きた証)
③郷愁や思い出を誘う活動(懐かしさ)
④災害対策活動(迷惑をかけない)
⑤その他(健康、趣味、楽しみ等自分の欲求を満たすこと)
自分の健康や趣味など、単純に自分自身の向上や楽しみのためというだけでなく、自分以外の誰かの為、社会や地域、次世代、家族などに役に立つように、自分の体験や身につけた能力、知識などを伝えたり、受け継がせたり、大げさにいえば、後世に残すべき使命を全うしたいという、意識の高さがあった。そして、そうした欲求を満たしてくれる場、自分の存在や能力を認めてくれて、共有し合える場を、自分の居場所として求めていた。災害対策や健康づくりなどは、自分のためであると同時に、他人に迷惑をかけたくないという意識も強くでていた。
こうしたことを受けて、テーマの選定や実施内容を考慮したところ、新規の方も含めた参加者数が増大し、特に後期高齢者の参加が増えた。
また、①参加者同士が顔を合わせる機会が増えたこと、
②一緒に作業を行い、ともに創り上げる一体感を味わったこと、
③参加者(聴衆)の共感を得たこと などから、
地域住民の間で絆が深まり、日頃の生活の中でも声かけの機会が増えたり、地域のために「場」を通じて行いたいことなど、積極的な提案が自発的に出てきたりと、意欲的な行動が見られるようになった。
(2)主体者としていきいき活躍できる場
「担い手」として、参画してもらえるような場面や機会を常に設定したことで、「場」の当事者である意識をもって、能動的に関わってもらえた。
特に体験談イベントでは、入念な事前準備(打ち合わせ、発表原稿まとめ)、大勢の前で話をすること、それが文章化(小冊子)して残るという、普段あまり経験のないことを行ったことで、発表者自身にとっておおいに刺激となった。
次世代に語り継ぎたい思いを披露することで、使命を果たした充実感と、人の役に立つことの喜びを味わい、聴衆の共感を得たことから、一定の満足感や達成感によって、生きることへの自信を取り戻すことができ、また、そのことを目の当たりにする、発表者以外の高齢者にとっても、地域活動への主体的参加意欲を高めることができ、体験談イベントの継続開催への布石となった。聴衆にとっては戦争や災害について、身近な方が実際に体験した話であったため、臨場感をもって受け止めることができ、改めて戦争や災害について真剣に考える場となり、また生きる勇気や人生への活力になったとの声を頂いている。
また、自分の特技を使って積極的に社会活動を行っている高齢者「ことぶきマスター」(リンク)の登壇により、いくつになっても、自分のできることをできる範囲で行うことで、自己実現できる可能性を示した。
このように、高齢者が活躍する機会を意識的に作ることは、当初は活躍の場を与えられるという、受動的な立場であるが、その責任を全うするために自然と能動的な関わりをするようになり、イベント後も、継続して積極的に関わったり、生活全般に亘って意欲的になったりする傾向が見られた。このことから、きっかけづくりやその方に適した活躍の場を提供することの重要性が示され、支援者のプロデュース能力の必要性も示唆された。
(3)地域との強い絆づくり
アンケート結果によると、調査対象者の8割以上が本事業によって地域との絆が深まったと回答していること、声かけマップの作成により、一人暮らし高齢者を含む高齢者単独世帯など、さつき野区に暮らす要声かけ全世帯が把握できたこと(彼らへのアプローチが可能になったこと)、訪問声かけの実施、要援護者も含めた避難誘導訓練の実施などから、本事業の掲げる地域力再生を通した、社会的孤立ゼロに向けて、事業が順調に進んだといえる。
避難誘導訓練は、今までなかなか実現できずにいたが、今回、本事業をきっかけに
①初めて実施できたこと、
②訓練を行うことで、地域の自治会、多世代住民、医療・福祉関係者、大学、消防団など多くの方々、機関との顔の見える関係作りができたこと、
③特に高齢者や要介護者が参加したこと で、
今後地域の中で具体的にどのように災害対策を行っていったらよいかを考えるための土台ができ、地域全体で話し合おうという機運が高まった。
高齢者や家族が気軽に集うことができる、意向に沿った「場」が充実(質・量の向上)していくことが、絆づくりに有効であったことはもちろんであるが、「場」づくりを進める過程そのものも、住民一人一人が地域と向き合うよい機会となることがわかった。また大災害時でも機能するような互いに支え合う、新たなネットワークや信頼関係の構築への一歩ともなった。
(4)関係各所との信頼関係の構築と継続的な連携強化
「場」づくりにあたり、テーマによっては、関係者や専門家の協力や支援を受けることで、充実した内容や安全性の確保等が図られる。本事業においても多くの関係者の手助けにより効果的に事業を進めていくことができた。
災害対策においては、消防団員や医療・福祉関係者、要援護者の避難誘導訓練に慣れた企業が加わることにより、要援護者への安全な対応が可能となり、安心して参加してもらえることになった。主催者としても心強く、欠かせない連携であった。
また、支援者側からも、例えば、医療・福祉関係者にとっては、要援護者の避難誘導訓練に関われたことは実務経験として学ぶべきことが多く、大変有意義であったとの感謝の声を頂き、双方にとって有意義な活動であったことが伺える。本事業での出会いをきっかけに、今後もさつき野区で継続的なお付き合いが進み、連携が強化されることが示唆された。
(5)地域力の育成
地域防災計画では町会、自治会等を中心とした、自主防災組織が身近な地域の初動対応の中心的役割を果たすことが期待されており、すなわち、災害時の在宅要援護者の救出や避難誘導などは、地域の近隣住民の手助けによるところが大きい。これは阪神淡路大震災時、行政による救助活動に限界があり、ほとんどの救助活動が地域の手で行われたことからも明らかであった。その後「市民が居住地で抱える生活問題に対して共同で解決していく力」を意味するものとして、地域力という概念が生まれた。
地域力は
①地域における活動の積み重ね、
②住民自身が地域の抱える問題を自らのこととして捉え、組織的な対応により解決する力、
③住民の地域に対する参加意識により培われるもの である。
低下している地域力を育み、再生させることが、課題に対して解決の一助になると考えられる。
本事業を展開した甲斐市さつき野区においても、新しい「場」の登場により、地域活動への参加者が増え、地域課題を我が事として捉え、我が地域をなんとかしたいという参画する意識が生まれてきた。「災害対策」では、声かけマップ作成や実際に声かけ訪問、避難誘導訓練等を行い、地域防災力の向上(自助の推進、互助の強化)が進み、「体験談イベント」では高齢者の体験談を伺うことで、地域住民間の連帯感が高まり、住民同士の絆が深まり、日常生活の中で自然な形で見守ることの大切さが浸透していったといえる。
(6)「場」を通じた、介護予防、自立支援、認知症予防等
高齢者の抱える課題解決
今後ますます増大する高齢者や要介護者を支えていくために、身近な地域の役割が重要になっていき、本事業においても「場」づくり活動自体が、介護予防や認知症予防、自立支援サービスになると考えられた。すなわち、「場」を作る活動そのものが深く考え、行動する機会となることから、そこに伴う人とのコミュニケーションや試行錯誤、外出の機会など全てが活動量を高めるものであった。また「場」は想定通り9つの機能(役割)を担っており、「場」で活躍することは、楽しみながら心身機能を向上させることができると考えられた。