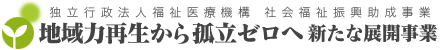1.受付名簿をもとに、参加者の氏名、所属(組)の確認を行う。
2.血圧測定・健康相談(山梨県立大学看護学部)(安全管理)
血圧の高めの方は、訓練では要援護者の役割を演じてもらい、車いすに乗って参加することとした。服薬しているにも関わらず、参加者の1割近くが血圧高めであった。日頃の健康管理(血圧コントロールや生活習慣の見直しなど)に留意が必要であることが明らかになった。
3.開会式
①はじめの言葉(本事業への理解、目的の共有化)
ⅰ)本事業の趣旨等についての説明(趣旨の理解)
ⅱ)さつき野地域における活動を支援する立場の再確認を行う
ⅲ)支援ネットワーク関係者の紹介
県立大看護学部(准教授:看護師、学生)
企業(人力車いすメーカー)、当法人(介護支援専門員、介護福祉士)
②オリエンテーション(安全確認、情報の共有化)
ⅰ)スケジュール、手順説明
・避難経路、休憩場所の確認 (前回セミナーで決めたコース等)
・グループ分けの説明(3グループ編成、各リーダーの紹介)
・全参加者のビブス着用(要援護者=オレンジ、支援者=グリーン)
・車椅子の操作方法について安全確認(グループ毎に専門職の指導)
・人数の確認(出発時、到着時)
ⅱ)留意事項について
・安全第一を心がけ、途中具合が悪くなったなど遠慮せず申し出ること
・ペットボトル、飴は一括してリヤカー等にて運ぶ
・記録用の写真へのご理解とご協力をお願いする
4.避難誘導訓練開始
①グループ編成 :グループリーダー等の紹介、車いす操作の確認
- ○リヤカーも大活躍
②一次集合場所を出発~避難所に到着(片道のみの避難訓練とし、帰りは乗用車にて移動)
1.さつき野公会堂(一時集合場所)出発 (目印場所)
2.さつき野団地前交差点 (スーパー(前))
3.柳田交差点 (コンビニ)
4.中下条公園 途中休憩(水分・飴補給)
5.敷島総合文化会館入口 (コンビニ)
6.西町交差点 (ガソリンスタンド) 7.敷島中学校(避難所)到着(~10:45)
・片道のみの避難訓練とし、帰りは乗用車にて移動
③炊き出し
④声かけ(一人暮らし高齢者等へのお誘いを行う)
⑤昼食・懇談
⑥防災セミナーと意見交換会
- ○ビブス緑は支援者、オレンジは要援護者
- ○狭い道も段差もありますね
- ○みんなでおにぎりづくり
- ○みんなで食べると美味しいね