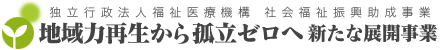*実際に避難所まで歩いてみよう!(要援護者と一緒に避難誘導訓練)
(大災害時高齢者等支援、心の拠り所、見守り、多世代交流、情報集散、仲間づくりの場)
11月30日(土)
当法人の介護職、山梨県立大学看護学部の協力により看護師、学生、地元の消防団員も加わり、車いす6台、杖の方3名、乳母車1台、リヤカー1台、要支援の方5名、後期高齢者18名の要援護者の参加があった。身体の状態で3班に分け、介護職、看護職、男性をバランスよく配置し、歩行に不安な方には介護職など付添い人が対応、車いす1台に付き、1.5名配置した。各班には先導する隊長としんがりを務める副隊長の役割を置き、列が長くなりすぎないように、また避難者の動向に注意を払うようにした。
行き先は集合場所のさつき野公会堂集会場から避難所の敷島中学校まで。通常通りラジオ体操を行った後(準備体操)、避難誘導訓練を実施した。片道通常なら20分位のところであるが、約1時間の道中となった。途中、公園で水分補給と塩飴で休憩。出発前には看護師、看護学生による健康チェックを行い、とにかく安全に事故なく戻ってくることを心掛けた。一人の脱落者もなく、全員で無事たどり着き、翌日の体調変化も特になかった。
帰りは車で戻り、おむすびを皆で握り、朝から用意した豚汁で昼食、初めて参加し方も多かったが、ともに出かけて、ともに食事をつくり、ともに食事をすることで、絆が深まったとのお声を頂いた。
地域で初めての避難誘導訓練となったが、①なかなか実現できなかったことができたこと、②地域の自治会、多世代住民、医療・福祉関係者、大学、消防団など多くの方々、機関との顔の見える関係作りができたこと、③特に高齢者や要介護者が参加したことで、今後地域の中で具体的にどのように災害対策を行っていくか、という機運が高まり、地域全体で話し合う機会につながっている。
- ○オリエンテーション