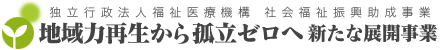*「場」づくり主体者の会(場の創造会議)の開催(場づくり支援)
11月29日(金)
10月24日の【地域のみんなで災害に備えよう!(1)】「見て、触れて、体験して、地域の防災対策を考える日」の実施を受けて、参加住民から自発的に要援護者を含めた避難誘導訓練を行いたい旨、声があがり、早速実行することになった。
実施にあたっては、なによりも「安全に行うこと」を優先することにした。特に今回は、「避難する時、何らかの援助が必要と考えられる声かけ対象とともに避難すること」を趣旨として行うことにしたことから(理由:①要援護者を含めた避難誘導訓練を実施したことがないこと ②前回の防災イベントにより地域内で災害時の要援護者対策が未整備であり、今後の取り組みとして必要性を感じたこと ③災害時対策は住民の共有しやすいテーマであり、避難誘導訓練をきっかけに多世代や閉じこもりがちな方やサロン不参加の方々にも声かけしやすく、参加協力も得やすいこと等)、避難誘導中の健康管理、けが、緊急時対応等に細心の注意が不可欠であり、事前準備を入念に行った。
1.計画案の検討
避難ルート、参加者・支援スタッフ状況、当日役割分担、手順・留意事項の確認、必要物資の準備・搬入、緊急時対応、健康管理、グループ分け、グループリーダー等の任命、雨天対応、帰り車手配、休憩地の確保、炊き出し準備、声かけ等
2.支援ネットワークの構築
地域の応援(さつき野区住民、消防団員、民生委員・児童委員他地域世話役の方々)
警察署、消防署等公的関係機関
山梨県社会福祉協議会(ビブスの借用、)甲斐市社会福祉協議会の協力
医療・介護専門職の参加(山梨県立大学看護学部、当法人)
隣接地区の応援(他地区いきいきサロン運営者など周辺地域の方々)
- ○場づくり支援コア人材の皆様
- ○避難経路の確認